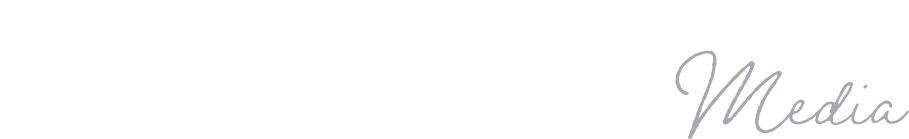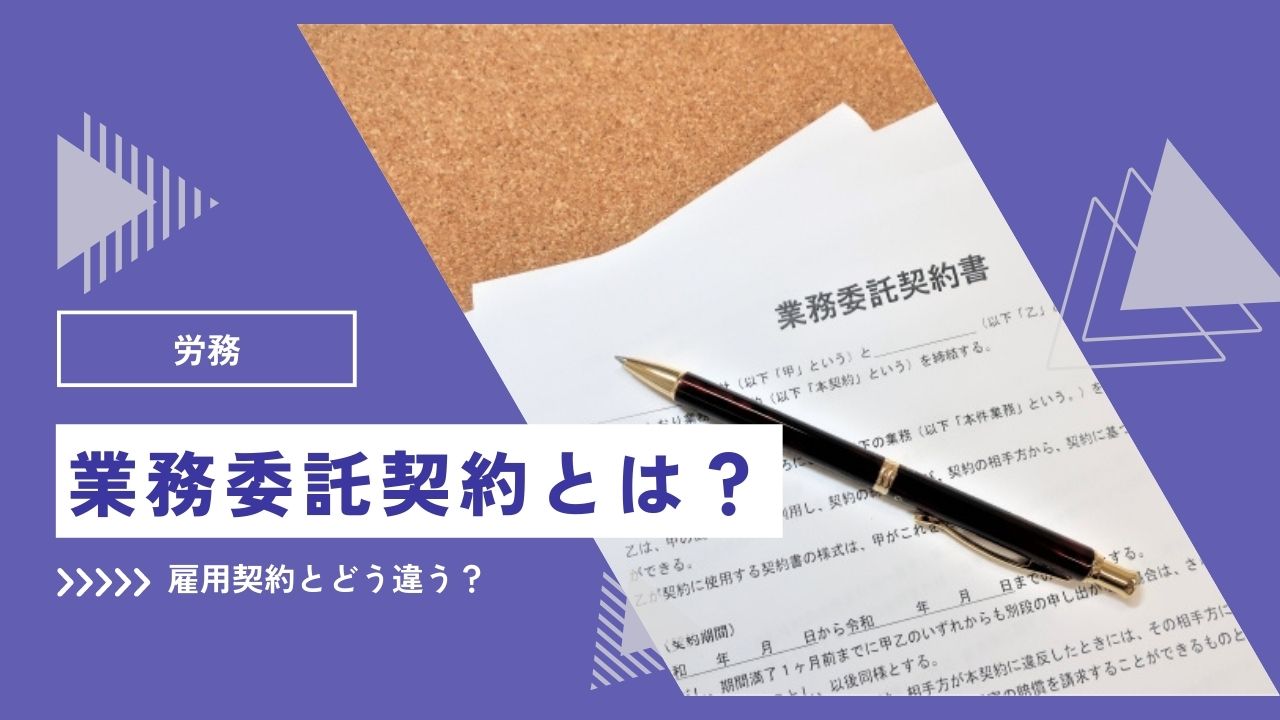偽装請負とは?判断基準・罰則と契約時に気をつけたいことを解説

前回の記事では、業務委託契約と雇用契約の違いについて解説しました。
業務委託契約を結ぶ際に気をつけたいのが【偽装請負】です。
この記事では、
- 偽装請負とは?
- 偽装請負の罰則
- 偽装請負の判断基準
- 偽装請負に陥らないために気をつけたいこと
についてまとめています。
偽装請負とは?どうして禁止されているの?
偽装請負とは
偽装請負とは、形式上は業務委託契約を結んでいるにもかかわらず、実態は雇用契約や派遣労働・労働者供給となっている状態のことです。
偽装請負の代表的な4パターン
厚生労働省東京労働局では偽装請負について、代表的な4パターンをまとめています。
- 代表型
- 形式だけ責任者型
- 使用者不明型
- 一人請負型
【参考:厚生労働省「あなたの使用者はだれですか?」】
中でもよく見られるのは「代表型」。
請負と言いながら、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤・勤務時間の管理を行ったりしているのがこのパターンです。
偽装請負に陥ってしまう原因
請負(業務委託契約)の場合は雇用契約とは違い、最低賃金などの労働基準法の適用がなく、社会保険の加入義務も必要ありません。
人件費や手間の削減のため請負契約をしたものの、実態としては業務についての細かい指示を出していたり、実際は自社の社員と同じように扱ってしまうことにより偽装請負の状態となってしまいます。
偽装請負はなぜ禁止されているの?
雇用契約であれば、労働者には労働基準法が適用され、
- 最低賃金や残業代
- 有給休暇
- 時間外・休日労働時間の上限
- 解雇制限
- 社会保険・雇用保険・労災保険に加入できる
などの保護が受けられます。
請負(業務委託契約)の場合はこれらが適用されず、
- 残業代が発生しない
- 有給休暇が取得できない
- 時間外・休日労働時間の上限が適用されない
- 急に注文を打ち切られる
- 社会保険・雇用保険・労災保険に加入できない
という不安定な立場に置かれます。
実態は派遣労働や労働者供給であるにもかかわらず上記のような状態になっていると労働者が適切に保護されないため、法律により禁止されています。
偽装請負に対する罰則はあるの?
偽装請負に対しては、労働者派遣法・職業安定法・労働基準法にて罰則が定められています。
労働基準法による罰則
- 未払いの残業代など
- 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(中間搾取の禁止)
偽装請負が実態的には雇用契約であると判断された場合は、労働基準法に基づく未払い残業代などが発生し、賃金未払いについて30万円以下の罰金(120条)が課される可能性があります。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
労働基準法第二十四条(賃金の支払)
また、「中間搾取の禁止」にも抵触する可能性があります。
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
労働基準法第六条(中間搾取の排除)
中間搾取とは、自社と雇用関係にない労働者を他社の指揮命令下で働かせることによって利益を得ること(いわゆるピンハネ)です。
中間搾取の禁止に違反する場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第118条)が課せられます。
労働者派遣法による罰則
- 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(無許可での労働者派遣事業の禁止)
労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。
労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
労働者派遣法第五条(労働者派遣事業の許可)
偽装請負が無許可での労働者派遣事業にあたる場合、派遣元事業主に対して1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます(59条1号)。
指揮命令権のない請負契約のはずが、派遣された自社の労働者と派遣先の間に指揮命令関係があると認められる場合には、労働者派遣であると評価されます。
職業安定法違反による罰則
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(無許可での労働者供給事業)
職業安定法では、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、労働者供給事業を行なうこと・供給される労働者を指揮命令下で労働させることを禁止しています。
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
職業安定法第四十四条(労働者供給事業の禁止)
労働者供給とは、自社と雇用関係にない労働者を供給契約に基づき他社に派遣して他社の指揮命令下で働かせることです。
無許可で労働者供給事業を行ない、偽装請負と判断された場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金(第64条9号)が課せられる可能性があります。
偽装請負の判断基準は?

契約ではなく実態を見て判断される
偽装請負にあたるかどうかは、契約の形式ではなく実態を見て総合的に判断されます。
本来、請負契約は会社(発注者)と労働者(受注者)に指揮命令関係のない対等な関係のはずが、実態として指揮命令関係にあると認められれば偽装請負だとみなされます。
偽装請負チェックポイント
指揮命令関係があると認められるポイントについて以下に具体的な例をまとめました。
- 仕事の進め方や時間配分について細かく指示を出している
- 仕事を行う場所が決まっている
- 勤務時間、休憩時間が決まっている
- 就業規則が適用されている
- 仕事に必要な備品を支給している
上記に当てはまるものがあれば指揮命令関係にあるとみなされ、偽装請負であるとみなされる可能性があります。当てはまるものがないかこの機会にチェックしてみましょう。
偽装請負にならないために気をつけたいこと

契約時に気をつけたいこと
- 業務委託契約書を正しく作成する
- 関係者に業務委託契約で仕事を依頼している旨を周知する
まずは契約時に指揮命令系統について留意しておくことが重要です。
契約内容から注文者が指揮命令権を持っているようなことがうかがわれる場合、偽装請負を疑われるリスクが生じます。
- 業務委託である旨を明記する
- 注文者にの指揮命令権があると疑われるような記載を避ける
これらの点に留意して契約を結びましょう。
また、現場の関係者にも委託する業務の範囲や偽装請負にならないための注意点を事前に周知しておきましょう。
業務を行う上で気をつけたいこと
- 定期的に現状を把握する
現場の視察・ヒアリングにより、指揮命令や勤怠管理など偽装請負を疑われるようなことが行われていないか定期的に確認しましょう。
まとめ
偽装請負は悪意がなくとも知らず知らずのうちに陥ってしまう可能性もあります。
現状の契約内容に不安がある方、業務委託を検討中の方はぜひご相談ください。